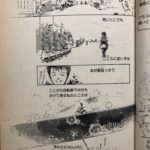私は街に出て花を買ふと、妻の墓を訪れようと思つた。(中略)その花は何といふ名称なのか知らないが、黄色の小瓣の可憐な野趣を帯び、いかにも夏の花らしかつた。(本文より)
深い悲しみが、静かで節度を持った言葉で包まれている。その表現の淡さ、控えめさの中に、封じ込められた悲しみと絶望、やりきれなさ、そして向ける場所のない怒りが伝わってくる。
能面のように、感情を封じ込めていなければ立っていられないのだと思った。
しかしそれでも、わたしはそこでこそ呼吸できる自分がいることに気づく。自分もまた死すべき存在であると自覚するから。
わたしはこの絶望の中でこそ、救いに出会わなければならない。この焼けただれ、瓦礫となった町で。
妻のために献げられた小さな花が一瞬の爆風の中に消滅するようなこの場所で、わたしは救いに出会わなければならないのだ。
わたしは、原爆が投下された日、この町に小さな「夏の花」があったことを忘れずにいたい。
著者の原民喜は、これを書いた6年後鉄道自殺した。
だからこそ救いはそこにあるべきだ。
絶望し自死する者が、妻の墓に名も知らぬ黄色い可憐な花を献げたという事実の中に、神はいなければならない。