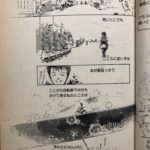わたしは相当人生に迷ってきたし、若い頃は仕事も中途半端な辞め方や始め方をしてきたと思う。20代の中ごろに長く入院せねばならなかった時期があって、医者からも予後も相当悪いと告げられていたので、どうせ誰でもいつか死ぬのなら、いっそのこと、「死ぬ」とは何か、「死んでいく」とはどういうことかを一度腰を落ち着けて考えてから人生を終わりたい、と思うようになった。20代後半のことである。
それから思いがけず病気が寛解し、徐々に普段通りの生活ができるようになり、通院しながらもサラリーマン生活を続けていたのだが、どうしても、あの「死ぬ」とは何か、「死んでいく」とはどういうことかについて一度腰を落ち着けて考えてみたいという思いが冷めることはなく、33歳のときに、ついに仕事を辞めてとある大学の3年次に編入学して学ぶことにしたのであった。
一度社会に出てからの、大学に戻っての学び直しはたいへんおもしろかった。しかし問題は学費や生活費の工面であった。大学近くのアパートを借りたこともあってその家賃も支払っていかねばならなくなった。
さいわい、日本育英会奨学金を借りることができ、勉強も頑張ったので返済義務のない奨学金などをいただくことができた。恥ずかしながら入学金を親に頼み込んだ(これについては別の機会に書くべき物語がある)。しかしそれでも生活費が足りない。学部生の頃は長期休暇時に新車を工場から販売店まで運転して届けるバイトや、毎晩、診察終了後の診療所とかクリニックを回って尿や血液を集めてまわる検体収集のアルバイトもした(誰もいない夜の病院の廊下を一人で歩くのは少し怖かった)が、本当に勉強しようとする身には、アルバイトで時間を取られることはつらかった。
院生になると「教学補佐」といって、授業を優先させて予定を入れ、その空き時間に学部図書室で座っておればよい、という大学が雇用する受付当番のアルバイトをさせてもらえた。当番と言ってもとくにすることはなく、本を借りに来た学生にカードを渡したりハンコをついて本を貸し出すくらいの仕事である。暇なのでたいていは受付に本を広げてレポートを書いて過ごした。
このアルバイトは授業を優先させてシフトを組める上に、勤務中も暇なので自分の勉強をすることができ、月8万円以上の収入にはなったのでアルバイト希望者は多く、成績不良者は申し込むことができなかった。
わたしは運よくこの仕事にありつけたのだが、ある日、何かの折に大阪道頓堀の戎橋――通称「ひっかけ橋」(グリコの看板のある大阪の観光地)――を通った時、そこで橋の両側に座り込んで似顔絵を描いたり、歌を歌ったり、バルーンアートをしたり、ミサンガを売ったり詩を売ったりしている若者があふれている光景に出会った。わたしはそこで、数年前に少しはじめながら大学編入で止めてしまった鉛筆画イラストをもう一度ここでやれないかと思いつき、さっそく次の週末から画材を持って「ひっかけ橋」にやってきた。
しかし初めてのわたしには、どこに座ればよいのか、勝手に座ってもよいのか、ショバ代などいらないのだろうか、まったくわからない。誰かに尋ねようと思ったら、ちょうど橋の端っこに、日雇い労働者風の前歯の一本抜けた人のよさそうなおっちゃんが紙に「自分の詩」を書いて売っていたので、聞くと、「ここに座ったらええわ」と自分の隣の空いているスペースを指さしてくれたので、まずこのおっちゃんの隣で描かせてもらうことにした。2002年の春の、とても日差しの強い日だった。
おっちゃんが、前歯の一本抜けた顔でどんな詩を書いていたかもう思い出せないのだが、おっちゃんの目の前の空き缶には百円玉や十円玉が何枚か入っていたことだけはハッキリと覚えている。「これで一食分くらいのメシ代になるやろ」と言っていた。
このおっちゃんの隣でわたしの鉛筆画修業がはじまった。しかしいきなりうまくいったわけではない。実をいうとある夕方に酔っ払いに絡まれそうになったことがきっかけで絵が売れるようになったのだ。そのことは次回書く。
ここでいろんな人との出会いがあった。楽しいことも、怖い思いもした。数本の鉛筆と消しゴムだけで、客の前でライブで絵を描く。精緻な鉛筆画似顔絵を15分くらいで。
描き終えるまでうまくいくかどうかわからない。描き始めてみなければわからないのだ。毎回そんな絵を描いた。この橋の上でそんな刺激的な修業をすることになったのだった。
おっちゃんはこの日の夕方前にむしろを丸め、数百円の売り上げを持って早々と帰っていった。それ以来おっちゃんと会うことはなかった。
(つづく)