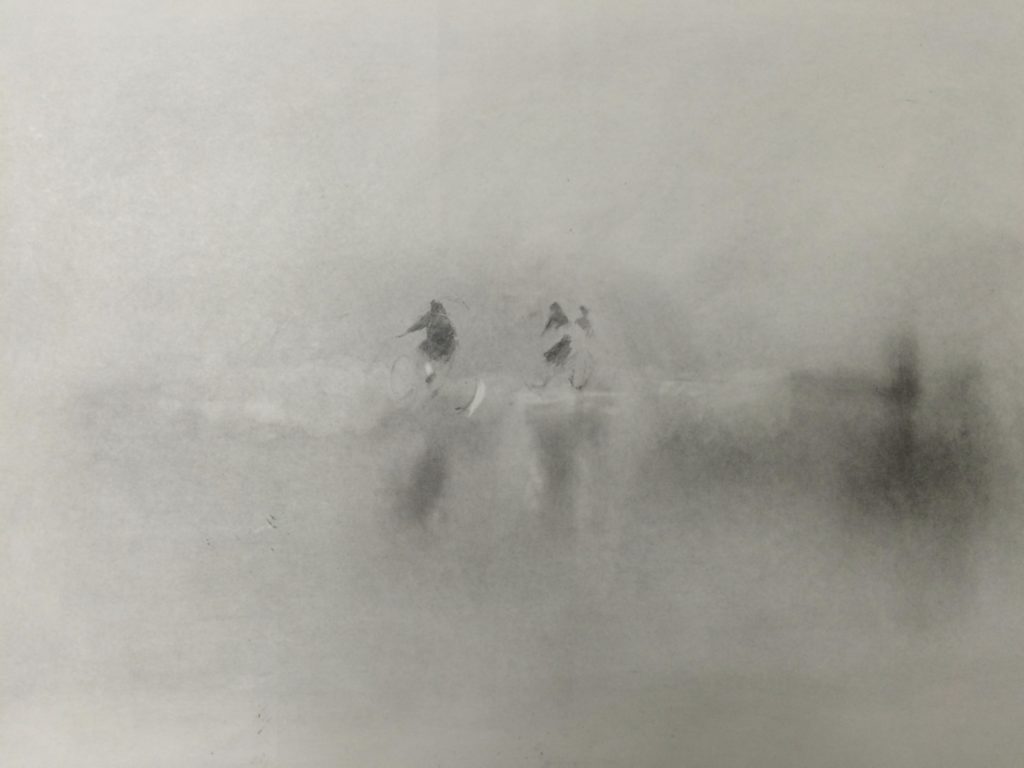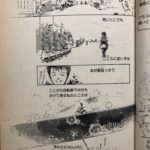1996年、奈良県立美術館で開催された「印象派の巨匠展」で出会った一枚の絵があった。絵の前で立ち止まってしまい、いつまでも引き込まれるようにその絵を見つめ続けた。ギュスターヴ・カイユボットの『ジュヌヴィリエの平原、黄色い野原』という作品だった。
何ということのない絵、と言えるのかもしれない。絵の中に劇的な要素はまったくない。はるか向こうに霞む地平線が広い花畑と空とを区切っているだけである。快晴ではない空。遠近法によってやや不安定な中空へと焦点を結ぶ畑の畝。
フランスの片田舎を描いたその光景は、しかし不思議にも遠く離れたこの日本の、高校時代の教室からよく目にしていた運動場や山の稜線と、それを見ていた当時の自分の感情さえも思い出させるのであった。気がつけば、もう絵の前で30分以上が経過していた。

出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)
そこには、花畑の畝と地平線、そして空が描かれていた。でも、カイユボットは、それらを通して、そこに吹き込んでいた穏やかな風や鳥の鳴き声、草いきれを――つまり描けないものを――描いたのかなと思う。さらに言えば、それを見ている自分の心の内側を。
家に帰って、鉛筆と練り消しを用い、さっそくケント紙に絵を描いた。雨の中を自転車で下校する高校生たちの印象だけをモチーフにして。それがこの絵である。カイユボットとは似ても似つかない(というか、カイユボットと比べること自体愚の極みであるが)。
でも、間違いなく、カイユボットの『ジュヌヴィリエの平原、黄色い野原』の印象が、わたしに「印象」を描くことを教えてくれた。対象を掘り下げて掘り下げて印象の世界にまで潜っていくことの感動を。
以来、このようなタッチの絵を何枚も描いたけれど、そのエッセンスはすべてこの最初の一枚にすでに含まれているような気がして、この未完成で心もとない一枚を私の鉛筆画の象徴であり源流として、今も大事にしている。